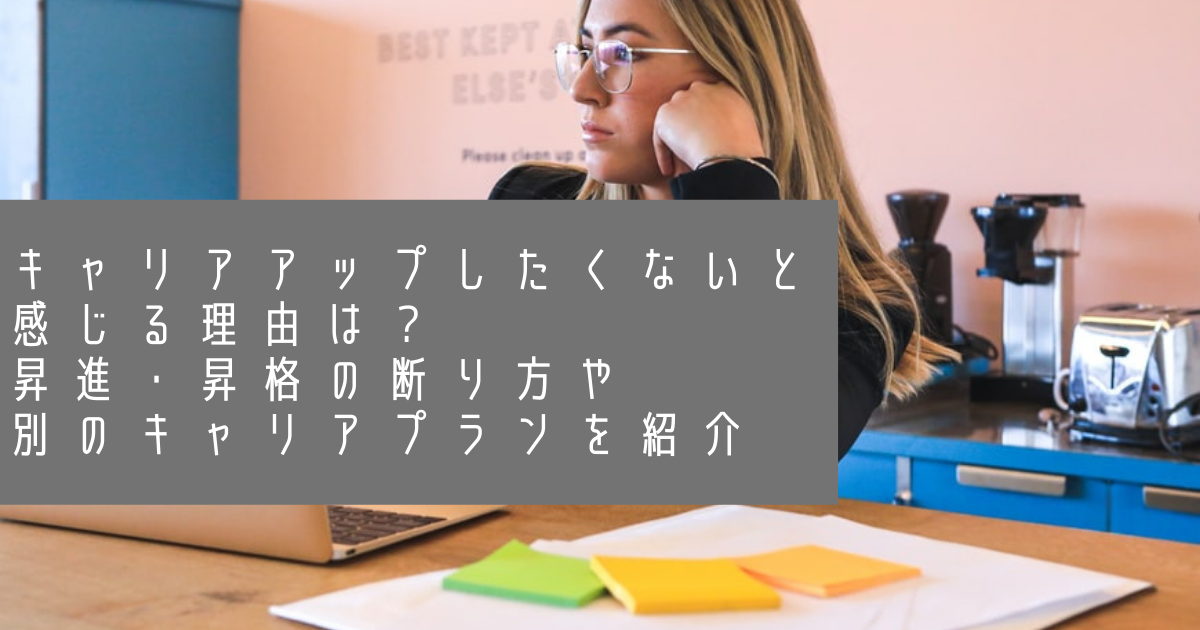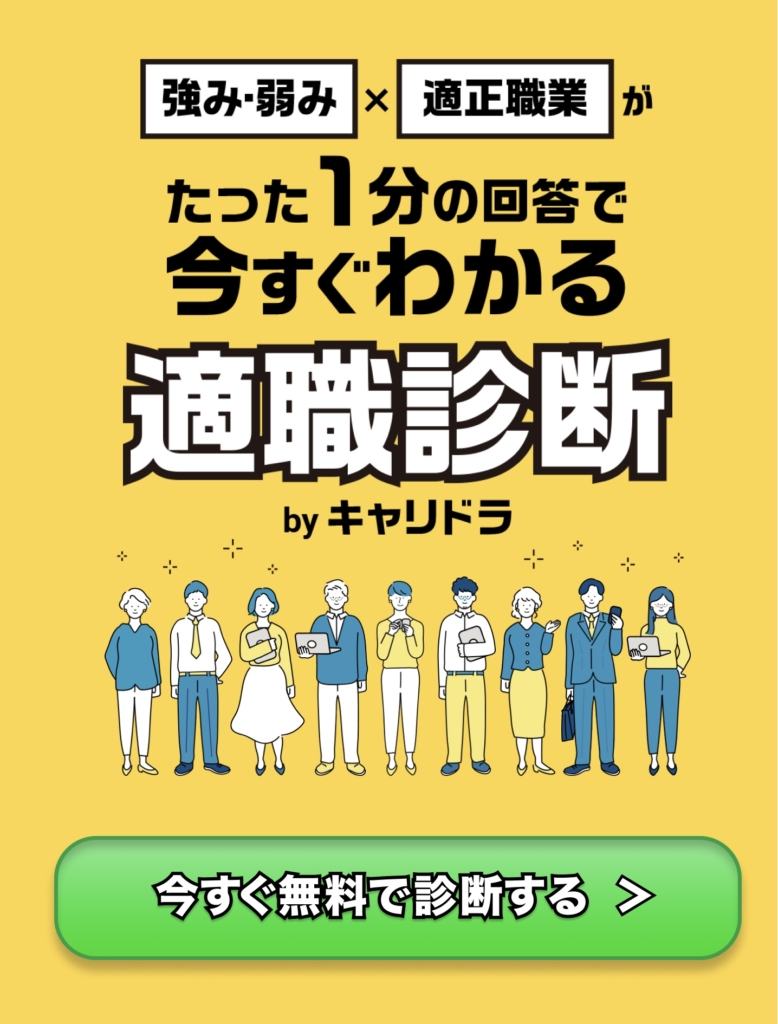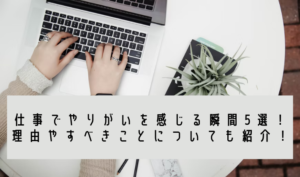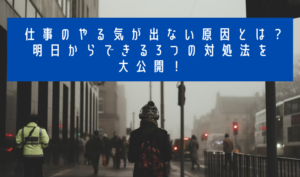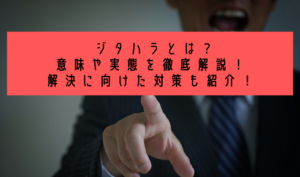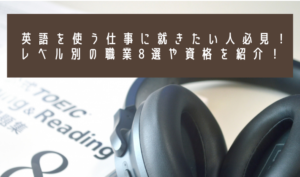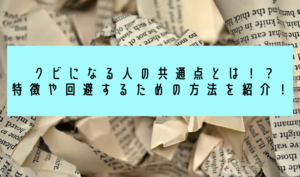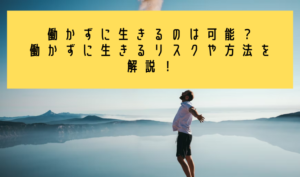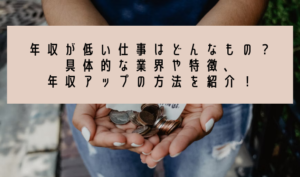「キャリアアップに魅力を感じない」、「上司に昇進を打診されたけど、できれば断りたい」とお悩みではありませんか?
近年、特に若い人達の間では「キャリアアップしたくない」と感じる人が増えているようです。
そこで今回は、キャリアアップを拒否したいと感じる理由や上手な断り方、キャリアアップ以外のキャリアプランについて紹介します。
キャリアアップしたくない人が増えている? 5つのキャリアアップを望まない理由を紹介

冒頭の通り、近年では若年層の間で「キャリアアップしたくない」と考えながら働いている人が増えています。ここでは、キャリアアップを避けてしまう理由について紹介します。
- 今の会社で働き続けようと考えていないため
- 「責任のある立場」にプレッシャーを感じるため
- プライベートや趣味の時間を優先するため
- 現場で働き続けたいと考えているため
- 自分らしく生きたいため
1.今の会社で働き続けようと考えていないため
まず考えられるのは、「今の会社」に残り続けてキャリアを積む気が無い事が理由の可能性です。
他にやりたい仕事があったり、業務内容や職場との相性が悪い、福利厚生面に懸念があるなど様々な理由で転職や退職を考えている場合、今の会社でキャリアアップを考えるのは難しいものです。
また、不安がなくても漠然と「この会社でずっと働き続けるのか」と考える人もいるでしょう。
このように現在勤務している会社に残る意思がない場合、キャリアアップの話が来ても「したくない」と感じてしまうのです。
2.「責任のある立場」にプレッシャーを感じるため
キャリアアップを避ける人の中には、昇進や昇格によって「責任のある立場」になりたくないと感じる人も少なくありません。
昇進によって、仕事に対するプレッシャーが増すと考えているのです。
例えば、キャリアアップによって仕事の裁量が広がり、より専門的な仕事に取り組む人もいれば、仕事量が増加したり、これまで以上に失敗が許されない仕事に就く人もいるでしょう。
また、管理職として他の社員の指導を任される場合もあります。
これらを重圧と感じ、「自分には務まらない」、「そんな責任のある立場になりたくない」とキャリアアップを拒否してしまうのです。
3.プライベートや趣味の時間を優先するため
ワークライフバランスを重視する価値観の広がりにより、「プライベートや趣味の時間もしっかり確保したい」と考える人が増えています。
この考え方が、時に「キャリアアップしたくない」と感じる事に繋がります。
キャリアが上がり仕事が増える、もしくは他の社員を管理する立場に就くと、生活において仕事の割合が大きくなりがちです。
その結果、「仕事が増えて趣味やプライベートを楽しむ時間がない」、「休みがなかなか取れない」という状況になる事もあるでしょう。
キャリアアップに対して上記のようなイメージが強く根付いている人は特に「仕事に生活の大半を費やすのは嫌だ」とキャリアアップを避けてしまうのです。
4.現場で働き続けたいと考えているため
現在の仕事や職場、働き方にも問題がない場合、「現場での仕事を続けたい」と考えているのが理由かもしれません。
「今の仕事が楽しい」と感じている人の中には、現在のポジションだからこそ業務に専念できるという場合もあるでしょう。
従って、キャリアアップによって業務内容が変わってしまうと今の仕事ができなくなると不安に思い、「キャリアアップしたくない」となる可能性が高いのです。
5.自分らしく生きたいため
最後に、キャリアアップを避ける理由に「自分らしく生きたいから」と考えているケースが挙げられます。
趣味やプライベートに限らず、仕事のペースや内容、働く場所全てを自分が納得した上で決めて生きたいと感じている場合、キャリアアップによって宛がわれた役職に就く事は納得できないと考える場合があります。
どの会社で働くか、どう働くかを常に自分で決め、自分らしい生き方を実現したいと考える人にとって、キャリアアップはあまり魅力的に感じないかもしれません。
「キャリアアップをしない」選択のメリット・デメリットは?

「キャリアアップをしない、断る」という選択をした場合、メリット・デメリットがあるのはご存知でしょうか。
それぞれをきちんと把握しておけば、選択の後悔を防ぐ事に繋がります。
キャリアアップを選択しないメリットは、「同じ業務を続けられる」、そして「仕事と趣味・プライベートの両立がしやすい」点であると言えます。
入社してから毎日コツコツ続けてきた仕事は、慣れやスキル、経験の積み重ねにより余裕を持って取り組めます。
また、業務の効率化も図りやすいため、余暇の時間を作る事も可能でしょう。
それに対してデメリットは、主に「収入が上がりにくい」事です。昇進・昇格によって給与が変動する事がないため、どんなに経験やスキルを重ねても収入に反映されにくい場合があります。
周囲のキャリアアップを選択した同僚との収入の差に、「やはりキャリアアップを選ぶべきだった」と感じてしまう可能性はあります。
キャリアアップを薦められたらどう断る? 上手な断り方のコツを紹介

ここからは、会社でキャリアアップを打診された際の上手な断り方のコツを解説します。
現在の会社で働き続けたいと考えている場合は特に、円満な断り方を目指すべきでしょう。
- 前向きな理由とともに、今のまま働き続けたいと伝える
- 自己評価を元に断る
- 嘘の理由で断らない
- 断る際は感謝を忘れない事
前向きな理由とともに、今のまま働き続けたいと伝える
まずお薦めの断り方は、「前向きな理由を添えて今の仕事を続けたいと伝える」事です。
現状に満足している旨を、明確な理由と共に伝えるのが効果的です。
例えば、「今の現場での仕事にやりがいを感じている」、「今の業務の中で、もっと実力を付けたいと思っている」など、ポジティブな理由と共に断る事で、キャリアアップを薦めてきた相手も納得しやすいのです。
自己評価を元に断る
もし、自分の能力が昇進に足るものではないとプレッシャーを感じているのであれば、その気持ちを正直に伝えるのも有効です。
「キャリアアップ後の仕事内容に対応できる自信がない」、「自分よりも昇進に相応しい人物はいる」と素直に打ち明ける事で、上司も「自信がないのであれば仕方ない」と引き下がってくれる可能性が高いでしょう。
会社側が本人の能力だけでなく「意欲」を重視している場合は、より適した方法と言えます。
嘘の理由で断らない
キャリアアップを断る際に注意すべきなのは、決して「嘘の理由で断らない」事です。嘘をついて回避した場合、後のトラブルに繋がる可能性があります。
例えば、嘘をついて昇進や昇格を断ったとします。
その時は円満でも、何かの拍子に嘘がバレてしまった場合、「キャリアアップを断った」以上に「会社に嘘をついた」のが問題になりかねません。
昇進や昇格はしなくても現在の会社で働き続けたいと思っている場合は尚更、断る際に嘘をつくのは避けるべきでしょう。
断る際は感謝を忘れない事
最後に、どんな断り方でも必ず意識したいのが「感謝の気持ちを伝える」事です。
例え会社の意に沿えずとも、感謝を伝える事で円満に話を薦められます。
会社や上司は、あなたの仕事への意欲や実力、将来性を見込んでキャリアアップの話を持ち掛けています。
そのため、自身の能力や意欲を評価してくれた事、評価に見合う立場を用意してくれた事に感謝すべきです。
感謝の気持ちを添える事でより穏便に話を断る事ができるため、その後の仕事も続けやすくなるでしょう。
過度にキャリアアップを避けるのは「出世したくない症候群」の可能性も

「現場で働き続けたい」や「他に目標がある」など、明確な理由でキャリアアップを避けるのではなく、特に理由はないけどキャリアアップしたくない、やる気がないという場合「出世したくない症候群」の可能性があるため注意が必要です。
この状態の特徴は、仕事そのものへの意欲が湧かなかったり、仕事なんて誰がやっても同じだと感じモチベーションが不足している点です。
この場合、現在の仕事が自分に合っていなかったり、仕事に対して主体的に取り組めていないなどが原因となっている可能性があります。
「出世したくない症候群」を放置し続ける事は、周囲との軋轢を生んだり自身の成長を遠ざける事態にも繋がりかねませんので、少しずつでも自分のやりたい事や仕事を探してみると良いでしょう。
出世以外にも道がある! キャリアアップ以外のプランを考えよう

キャリアアップを断った後に重要なのは、「キャリアアップ以外のプランをきちんと見据えておく」事です。
現状維持も悪くはありませんが、今後自身の価値観が変わる事も考慮し、様々な選択肢を持っておくべきです。
例えば、現在の仕事、立場でのプロフェッショナルを目指して知識や経験を重ねるのも良いですし、会社に属する事にこだわりがないなら独立を、現在の会社以外でやりたい事があるなら転職を考えるのもお薦めです。
いずれにしろ、希望する選択肢を選び取れるよう、知識やスキル、経験を無駄にせず積み重ねていくと良いでしょう。
まとめ
「キャリアアップしたくない理由」は人によってそれぞれです。
そのため、自分が何故したくないのか、その理由を明確にしましょう。理由が見つかる事で、キャリアアップに限らず今後のキャリアプランの設定にも役立ちます。
そして、もし現在会社で昇進についての打診があり、効果的な断り方を模索しているならば、ぜひ今回紹介した断り方のコツも参考にしてみて下さいね。
「キャリアアップ以外の選択肢がわからない」、「自分がやりたい事がまだ見つからない」とお悩みなら、ぜひキャリドラに相談してみませんか。
キャリドラは転職や働き方、キャリアアップなど、仕事に関する様々な相談、サポートに対応しています。
キャリドラの利用を通して、自身のやりたい事やキャリアプランが見つかるかもしれません。